『「匠の技 伝承」プロジェクト2022年度第2回指導者養成講習会』開催
2022年9月4日(日)、日本柔道整復師会会館(東京都台東区)において、『「匠の技 伝承」プロジェクト2022年度第2回指導者養成講習会』が開催された。本講習会は橈骨遠位端骨折・肩甲上腕関節脱臼を重点部位とし、対面受講・オンライン受講併用のハイブリッド方式にて行われた。


(公社)日本柔道整復師会・伊藤述史会長は‶皆さんもご承知のように社会から今、柔道整復師の資質の向上が求められている。骨折、脱臼の患者さんが多く来院され、先輩から叱られながらもしっかりと整復・固定の勉強ができた時代もあった。しかし現在は、接骨院・整骨院から包帯を巻いて出てくる患者さんは殆どいない。地域住民の信頼を得るためにも、我々の生命線である外傷の治療、特に骨折の整復・固定をしっかりと学び、各地域で提供できる体制を整えていきたい。そのような考えで『匠の技 伝承』プロジェクトは始動した。現在、我々日本柔道整復師会は、料金体系の抜本的見直し、受領委任払い制度の堅持、電子請求の推進等に取り組んでいるが、それらを進めるためにも国民からの信頼が不可欠だと考えている。皆さんと協力しながら「頑張る人が報われる、明るい柔道整復業界」にしていきたい。皆さんの今後の活動に期待している〟と挨拶。

長尾淳彦副会長は〝新型コロナウイルス感染症が流行するなか、『匠の技 伝承』プロジェクトではオンライン方式やハイブリッド方式での開講をはじめとする様々な策を講じながら、骨折・脱臼の整復・固定を一緒に学んできた。応急手当といえども骨折・脱臼を診ることができるのは医師以外では柔道整復師だけであり、これを手放すべきではないとの想いから、10年計画でこのプロジェクトに取り組んでいる。ただ単にこの講習会に参加されている方にだけ教えるということではなく、ここに参加されている方々に今後指導者となっていただき、各都道府県でその技術を伝えていただくことを目的としている。この十数年間、近所の施術所で骨折・脱臼の治療を希望される患者さんが来院しても「治療できないので病院に行ってください」と手放すような状態が続いていたが、全国どこでも平準化した施術が受けられるようにしていきたい〟と意義を語った。
実習に先立ち、森川伸治学術教育部長は、指導者評価について〝参加される先生方の技能を評価するわけではなく、あくまでもこれから柔道整復師の指導者として活動していただくための評価を行う。骨折・脱臼は常日頃から遭遇するものではないからこそ、本日学んだことをしっかりと身に付けて指導者となっていただきたい〟と前置きしたうえで評価方法の説明を行った。
実技評価のポイントについては、講師の山口登一郎氏から整復・固定技術について、佐藤和伸氏からエコー画像描出操作について説明が行われた。山口講師は‶術者と患者の位置、整復時の患者の肢位、患肢の把持・転位および原因・合併症または後遺症の説明、整復法や整復手順・整復後の保持が適切であるか等を確認する。患者は背臥位とし、膝関節を屈曲させる。患肢は60度外転し、肘関節は90度とし、手首を上手く把持すること。また、今後指導者となることを念頭に置き、必ず口述しながら動作すること〟、佐藤講師は‶プローブを持つ際は第4指・第5指が患者の肌に触れるようにすると安定する。まず上腕骨に対して短軸走査で結節間溝を描出する。小結節、大結節、その間に上腕二頭筋腱の長頭腱がある。上腕二頭筋腱を描出する際は、低エコーとならないよう入射角に気を付ける。さらに大結節から90度回転させて、肩峰・棘上筋腱・棘上筋腱の付着部を描出する。橈骨下端は、中枢から末梢まで高輝度の線状高エコーとなるように描出すること。まずリスター結節を描出し、掌側には橈骨遠位端から舟状骨、やや尺側に移動すると月状骨が描出される〟と説明した。

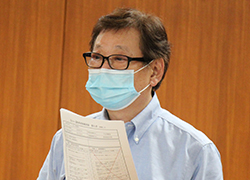

その後、受講者全員で固定材料を作成し、その材料を用いて整復・固定操作技術とエコー画像描出の合同実習が行われた。




実習後は、指導者評価確認として橈骨遠位端骨折および肩甲上腕関節脱臼に対する整復・固定・エコーの評価確認が行われた。


森川学術教育部長は〝実際の患者さんへの施術と実習とではかなりの違いがある。患者さんの年齢や状態はそれぞれ違うため、力の加減によっては却って症状が悪化してしまうケースもある。そのような点も含めて、先生方には様々な症例で検証していただきたい。何度も何度も繰り返しトレーニングを行わなければ習得できない。骨折・脱臼の施術数は少なくなっており遭遇することも少ないと思われるが、積極的に挑戦していただきたい〟と力強く述べた。

最後に、長尾副会長が‶経験豊富な先生でも、整復固定やエコーの評価を受けるとなると緊張感があったのではないか。今後は各地域で皆さんの指導を受けられる先生方にも、緊張感をもって受講していただける研修にしていきたい。また現在、柔道整復業界でエコーを導入している施術所は4千件強であるが、より多くの施術所に導入されることで堂々と扱うことができるようになる。ぜひ普及に努めていただきたい〟と総括し、富永敬二理事の閉会の辞により終了した。
PR
PR